大学院のプログラム
プログラムの特徴
国際文化交流の専門家に必要な実践能力・研究能力・問題解決能力を備えた人材を育成するため、以下の4つのプログラムを提供します。
- 「アートマネジメント」プログラム
- 「国際協力」プログラム
- 「日本学・比較文化」プログラム
- 「国際関係・地域研究」プログラム
「アートマネジメント」プログラム
【担当教員によるプログラム紹介】
アートマネジメントプログラムは非営利・営利の文化芸術事業のマネジメントに携わる人材を育成するプログラムです。
20世紀末に冷戦が終了しグローバリゼーションが加速されて以降、アートの分野でも国際化が進展し、非営利・営利の国際的な文化芸術事業(国際的芸術祭、現代美術館、オークション、ギャラリーなど)が急増しました。同時にローカルな文化の再認識の気運も生まれ、地域の文化を活性化する事業が始まっています。いずれの局面においてもアートマネジメントの専門家が必要とされる時代になりました。
本学大学院のアートマネジメントプログラムはこうした動向を踏まえて設置され、主に造形芸術と舞台芸術の専門家を育成してきました。アートマネジメントのファンダメンタルズに始まり、文化資源、文化経済、文化経営、非営利団体、アーカイブズ、パブリック・リレーションズなどアートマネジメントの専門家となるために必要な講義、研究、実務実習科目などを提供しています。
担当教員はアートマネジメントの実務に携わっている専門家であり、最新の研究成果、実務経験が反映された授業を受けることができます。院生の研究対象は指定管理者制度、行政の文化政策などの制度に関する課題、ミュージアムショップ、チケッティングなどの文化施設の経営の課題、コミュニティの文化活性化の課題など多岐に渡ります。
修了生は文化行政担当の公務員、文化施設(博物館、美術館、公共ホールなど)の学芸員・企画担当・運営担当、文化芸術の企画会社、企業ギャラリーの運営など文化芸術の第一線で働いています。
【担当教員紹介】

牧野 元紀(教授)|MAKINO Motonori
専門分野:博物館学(展示学、アートマネジメント、博物館史)、アーカイブズ学(書誌学、文献学)、東洋学(東西交流史、アジア近代カトリック史、太平洋海域史)
「芸術は長く、人生は短い」との格言がありますが、「芸術家の人生は短いものだが、その芸術作品は長く残るものだ」と一般には解されています。もともとは古代ギリシアの医学者ヒポクラテスの残した言葉です。原典はギリシア語ですが、ラテン語のArs longa, vita brevisのほうが古くから知られており、その日本語訳が上記として定着しています。
しかし、このArsという言葉とそこから派生した英語のArtですが、「技術や技能あるいは学術」といった意味を元来有しています。ヒポクラテスはそもそも医学者でしたから、むしろ「技術(学術)は長く、人生は短い」であり、「少年老い易く学成り難し」とでも訳すほうが「学術」的には正解です。リベラルアーツを掲げる本学でアートと芸術を等号で結ぶ方はいらっしゃらないでしょうが。
とはいえ、多義性に富むこの「アート」という概念、可視化や数値化とは相性が合わないことは否定できません。それでも人間社会を支える経済活動において何らかの意義付けは必要であり、そこに存在意義を主張しなくてはそれこそ「短い」ものとなってしまいます。当世風にいえば「サスティナビリティ」は最重視すべき課題であり、そのためにもマネジメントすなわち運営・経営という中長期的視点は必須となります。
私はこれまで国内外幾多の大学での研究教育活動に加えて、国立公文書館で3年間、東洋文庫にて15年間の勤務を経てきました。大学教員でありつつも、現役のキュレーターかつアーキビストとしてのアイデンティティを今も強く持ち続けています。特に東洋文庫ではミュージアムの立ち上げから軌道に乗るまでのマネジメント業務に関わっており、これまでに手掛けた数々の企画展はまさに「アート」の多義性を象徴する様々なテーマに及んでいます(東洋文庫ミュージアムホームページの「過去の展示」をご覧ください)。
「アート」を「マネジメント」するとなると、ついついプラグマティズムを追求しがちですが、その必要は全くありません。再びラテン語を用いますならば、Festina lente(「ゆっくり急げ」、すなわち「急がば回れ」)を強調しておきましょう。確とした本物のアカデミズムに裏打ちされた知識と教養はこれから先も決して古びることはありません。一生モノのArsを身につけられるのが本学大学院の強みです。さあ研究対象を見つけ、じっくりと向き合いましょう!
「国際協力」プログラム
【担当教員によるプログラム紹介】
国際協力プログラムでは、地域の自然環境や文化・価値体系への配慮、国際関係への理解等の国際協力に必要な専門知識及び能力の養成を目的としてカリキュラムを編成しています。具体的には国際協力プログラムに関する教員が、文化遺産の保全と活用、国際協力におけるNGOの役割、開発における「制度」の重要性、食糧をはじめとした資源とその利用など、それぞれの専門分野に関する演習を通じて国際協力の多様な側面に関する専門知識を提供します。加えて、費用便益分析、文化協力の企画立案、統計処理法、ドラフティング・プレゼンテーション、プロジェクトマネージメントなど、国際協力の分野において必要となる、実務知識や技能を横断的に習得できる科目を提供していることも、本プログラムの特徴の一つです。さらに、プログラム修了後の実務家としての活躍を支援するために、たとえば開発途上国の開発協力の現場などでのインターン研修の履修を推奨しています。また、本プログラムの演習科目の担当者が、世界文化遺産制度で有名なUNESCO、国際的な開発協力NGOでの勤務経験を有する、あるいは大学以外の教育・研究機関に勤務し、人材育成に寄与するなどのキャリアを持つ教員であることも、本プログラムが実務家養成に力を入れていることを示しています。
【担当教員紹介】

伊藤 由紀子(教授)|ITO Yukiko
専門分野:国際協力・援助、NGO・NPO
日本生まれの国際協力NGOで紛争後のルワンダ復興事業に携わってきました。その経験をもとに現場第一主義の国際協力活動の在り方を学生の皆さんと考えてきています。現場第一主義、受益者の主体性といった考え方と同時にリーダーシップというタームが重要視されていますが、多くの方には聞きなれない「フォロワーシップ」という概念が実は非常に大切です。グループや地域、組織等を引っ張るリーダーやそのスキルはそれだけでは成り立たないことは実は往々にしてあり、大多数のフォロワーがどのように行動するかにもかかっています。本プログラムは、実務家養成のための多様な科目を提供することを特徴としていますので、この「フォロワーシップ」についても考えていただきたいと思います。
国際援助は不可欠ですが、永遠に援助をすることは必要悪かもしれない、こういった視点も持ちながら、近年は「援助する」から収益事業を通したエンパワメントに主眼を置いてルワンダで活動をしています。
「日本学・比較文化」プログラム
【担当教員によるプログラム紹介】
「日本学・比較文化」プログラムは、本大学院の4コースの中で、とくに日本について深く学ぶコースとなっています。主に文学・歴史・社会・言語が対象となりますが、専門領域を越え、さらに過去から現代まで、広く学ぶことができることが特徴といえるでしょう。コースの名前にかかげている「日本学」(Japanology)は、欧米において異文化への憧憬、そして植民地政策を背景として誕生し、地域研究として発展してきましたが、その強みは文化研究としての総合性と他文化との比較の視点にあります。本コースにおける「比較」の意図するところは、異文化同志のいわば表面的な相違を探すのではなく、具体的な研究にもとづいた研究視座の獲得にあり、単なる日本研究ではなく、比較文化の視点を学べるカリキュラムとなっています。ぜひ、本コースで、専門分野の研究を深めつつ、広い視野をもってご自身の「日本学」を構築していただくことを願っております。
【担当教員紹介】
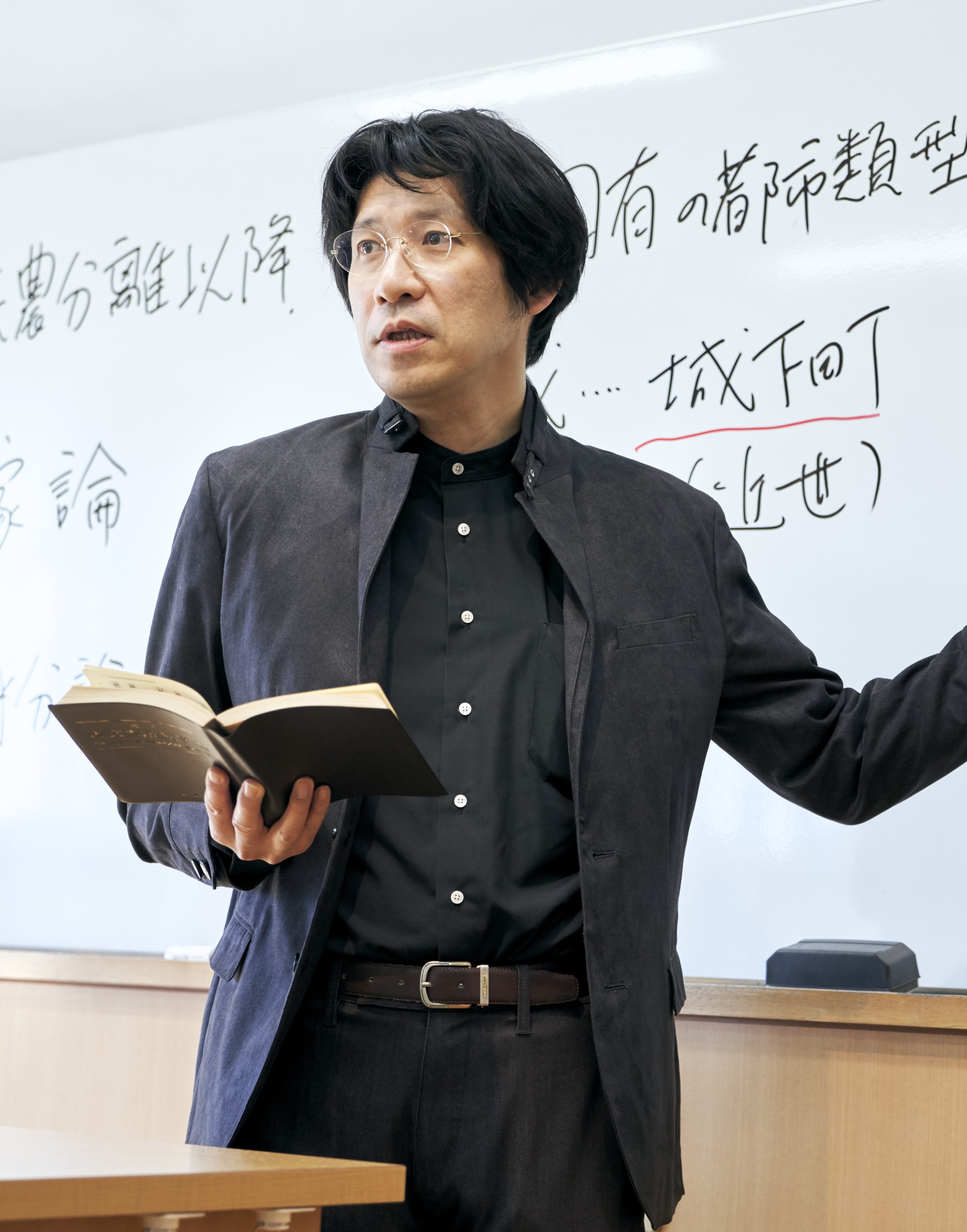
岩淵 令治(教授)|IWABUCHI Reiji
専門分野:日本近世史
専門領域は歴史学で、とくに古文書を素材として江戸時代の都市、とくに都市江戸の社会や文化を研究しています。とくに、都市における武家のありよう、町や商人の社会について研究をすすめてきました(『江戸武家地の研究』塙書房、2004年ほか)。こうした研究を続けていく中で、現代に至るまで都市江戸がどのように語られてきたのか(「江戸」の表象論)、さらに日本学が生み出されたヨーロッパにおける江戸の語られ方にも関心を持ちました。モノ資料を扱う考古学が研究の出発点にあったことと、国立歴史民俗博物館の勤務で、展示解説や、海外での日本展示にかかわった経験が大きかったと思います。こうした関心から、2016年には本学で仏・米・韓の日本史研究者を招き、「"日本史研究"のコンテクスト」というシンポジウムを開催しました(『グローバル・ヒストリーと世界文学』勉誠出版、2018年)。現在は、とくにフランス国立社会科学高等研究院(EHESS)日本研究所(CRJ)の所員を始めとするフランスの日本研究者の方々と研究交流をしています。
「国際関係・地域研究」プログラム
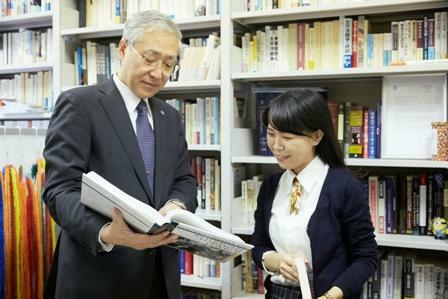
【担当教員によるプログラム紹介】
世界には独自の歴史的・文化的背景を持つ多数の国家・地域・民族が存在し、それらの相互関係、相互作用は複雑多岐にわたります。グローバル化が進展する現代、それらの結びつきはいっそう緊密さを増しており、私たちの日常生活から国家の政策に至るまでの一切が国際社会と切り離しては考えられません。国際文化交流に際しても国際社会への認識・判断が問われることは当然です。
このため、国際社会の構造・プロセスを様々な側面から分析して国際問題の本質を解明し、国際社会を構成するそれぞれの国家・地域・民族の特質について理解を深め、その対応についても検討することが必要不可欠になります。
これらの課題に応えるために必要なのが、「国際関係論」や「地域研究」の学問的知見です。
国際社会は複雑ですが、それは国家同士の政治関係、企業活動によっておこる経済関係、諸国家・諸民族の接触による文化関係、といったようにいくつかの断面の組み合わせからなっており、それらの諸断面の交錯している場と捉えることができます。
そこで、このプログラムでは、政治、経済、外交、安全保障、法律、経営、メディア、国際機構といった側面から国際社会の構造・プロセスや国際問題の本質を分析する「国際関係論」と、国家・地域・民族の特質を理解する「地域研究」のそれぞれの研究成果を結びつけながら、国際社会についての本質的洞察力、構造的理解力、多角的視野、動態的把握力などを養成することを目指します。
【担当教員紹介】

畠山 圭一(教授)|HATAKEYAMA Keiichi
専門分野:国際政治、アメリカ政治外交、日米関係
研究テーマを戦後日本の形成過程に定め、占領研究のために1986年に米国に留学し、その後ワシントンDCにある複数の大学及びコンサルタント会社の研究員として、約10年間、日米関係の調査・分析・政策立案にかかわってきました。この間の仕事は、当初の研究テーマとは違い、主に、安全保障・通商・技術に関する米国の政府機関(国務省、国防総省、商務省、通商代表部等)における対日政策動向や連邦議会における対日論議についての調査・分析を中心とするものでしたが、その後の研究にとっての大きな糧になったと思います。
米ソ首脳会談、冷戦終焉、湾岸危機・湾岸戦争、ソ連崩壊といった歴史的転換の場面をホワイトハウスや連邦議会の動きと共に見ることができたことや、時代潮流の変化の中で日米関係も急速に変化していく様を直接体験したことで、それまで学問の対象だった国際政治を自らの人生そのものに直結して考えられるようになり、歴史を体験として実感できるようになったからです。
1996年に帰国してからも、大学での研究・教育の傍ら、シンクタンクの研究委員や政府の諮問委員などとして、今日の国際情勢に関する委託研究調査、政策分析、政策提言の策定にも従事してきましたが、その中で改めて痛感し、あるいは共感したのは、私の研究対象である1940年代から50年代の激動期に国家の課題と真剣に向き合った指導者たちの生き方でした。
戦争と平和、貧困や環境問題など、今日の国際社会の動きは、私たちの生活に死活的な影響を及ぼします。各国の指導者の立場に立ちながら今日の国際情勢を見つめ、あるいはその時代の背景を深く考えながら歴史を見つめ、国家の課題と真剣に向き合っていく姿勢を確立することが、国際問題を扱う者として最も重要なことだと肝に銘じています。
